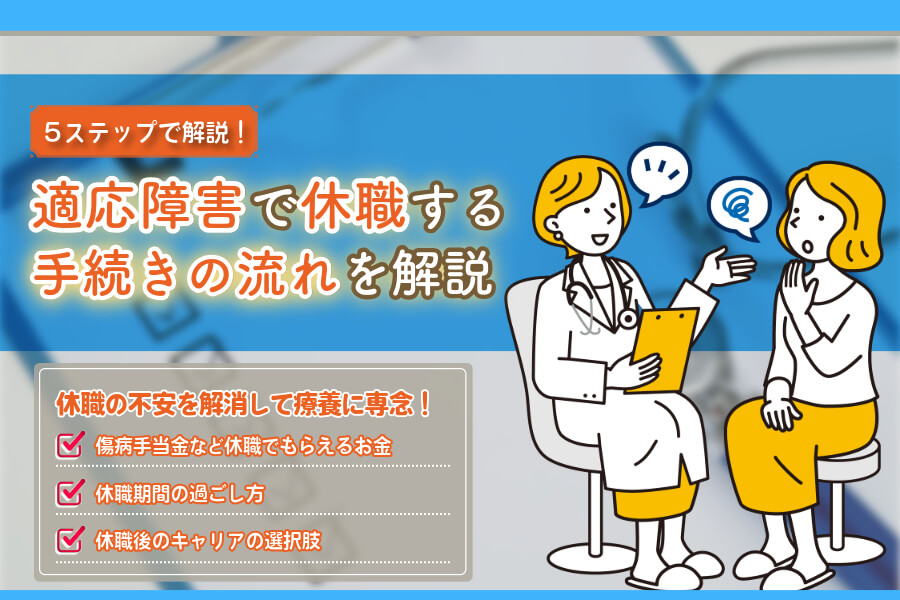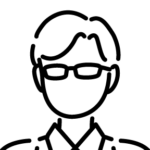
適応障害で休職したら周りに迷惑をかけてしまうのでは……
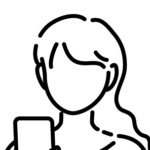
どうして自分だけがこんなにつらいのだろう……不安で毎日が苦しい……
適応障害で心身の不調を抱えていても、「会社に迷惑をかけてしまう」という罪悪感と将来への不安から、休職という決断に踏み出せない方もいるのではないでしょうか。
休職と聞くと、複雑な手続きやお金の心配、将来への不安が頭をよぎるのも無理はありません。
しかし、ストレスから心身に不調が生じる適応障害はストレスの原因から離れると改善することが多いともいわれています。
職場がストレスの原因なのであれば、休職することは適応障害を改善する一歩になり得ます。
この記事では、休職の準備から手続き、傷病手当金といったお金の話、回復に向けた過ごし方、そして復職や転職といったその後のキャリアまで、あなたが安心して療養に専念するための全ステップを解説します。
一つひとつのステップと利用できる制度を正しく知ることで、休職する不安を和らげましょう。
- 適応障害で休職するまでの具体的な手続き
- 傷病手当金の申請など休職中のお金の不安を解消する方法
- 回復の段階に合わせた休職期間の過ごし方
- 復職や転職など休職後のキャリアの選択肢
メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。
Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。
おすすめのオンライン診療内科3選
| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |
|---|---|---|---|---|
| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |
| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |
| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |
- 診断書の即日発効
▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート
▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申
▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/
【図解】5ステップで分かる!適応障害で休職する手続きの流れと休職後の未来までのロードマップ
先の見えないトンネルの中にいるような気持ちで、これからどうなってしまうのだろうと不安に感じているかもしれません。
ですが、過度に心配する必要はありません。
ここでは、あなたがこれから進む道のりを5つのステップに分けて、地図のように分かりやすく示します。
この5つのステップを一つひとつ確認していくことで、漠然としていた不安が「次に何をすれば良いか」という具体的な行動計画に変わっていきます。
最初のステップである診断書は、スマホのオンラインで完結させることが可能です。詳しくは下記を御覧ください。
メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。
Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。
おすすめのオンライン診療内科3選
| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |
|---|---|---|---|---|
| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |
| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |
| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |
- 診断書の即日発効
▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート
▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申
▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/
まずはあなた自身を守るための準備から、一緒に始めていきましょう。
休職の準備:適応障害の診断書のもらい方と会社へ切り出す前の心構え
休職を考え始めたとき、何よりもまずあなた自身の心と体の状態を客観的に把握し、専門家の助けを求めることが重要です。
この最初のステップが、その後の回復への道を左右します。
手続きを進める前に、まずは心の準備を整えましょう。
まずは心療内科・精神科を受診して医師に休職したい旨を伝える
心や体の不調を感じたら、勇気を出して心療内科や精神科を受診しましょう。
専門家である医師に相談することは、回復への確かな一歩です。
診断書をスムーズに発行してもらうためには、医師にいつから、どのような症状があり、仕事の何が原因でつらいのかを時系列でメモにまとめておくと伝わりやすくなります。
例えば、
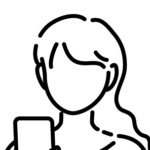
1ヶ月前から眠れなくなり、月曜日の朝に動悸と腹痛が起こる…
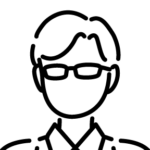
新しいプロジェクトの担当になってから症状が悪化した…
といった具合です。
| 診察で伝えるべきこと | 具体的な内容の例 |
|---|---|
| 主な症状 | 眠れない、動悸、めまい、食欲不振、涙もろい、何も楽しめない |
| 症状の時期 | いつから始まったか、特に症状がひどい曜日や時間帯 |
| ストレスの原因 | 長時間労働、職場の人間関係、業務内容の変化、仕事のプレッシャー |
| 生活への影響 | 仕事でミスが増えた、遅刻や欠勤、趣味を楽しめなくなった |
正直に、ありのままを伝えることが、適切な診断とあなたに合った治療計画につながります。
メンタルクリニックの受診がおすすめです

休職に必要な診断書の即日発行を希望する方は、Oops HEARTがおすすめです。
Oops HEARTでは精神科医による診察がオンラインで受診でき、診断書の即日発効に対応しています。
おすすめのオンライン診療内科3選
| クリニック名 | 診療費・診断書発行費用※ | 診断書の即日発行 | 営業時間 | 薬の処方 |
|---|---|---|---|---|
| Oops HEART 公式サイト | 4000円~ | 最短即日 | 10時~24時 | あり |
| ウィーミート 公式サイト | 10,000円~ | 1週間程度 | 9時~20時 | あり |
| ファストドクター メンタル 公式サイト | 8,000円~ | 当日~3日以内 | 10時~20時 | あり |
- 診断書の即日発効
▶休職手続きで必要 - 傷病手当金の申請サポート
▶休職時に利用できる制度 - 24時までの診察可能申
▶当日予約OK

\予約方法はLINE友だち登録のみ!/
会社に迷惑をかける…休職を切り出す「罪悪感」の乗り越え方
休職を考えるとき、多くの真面目で責任感の強い方が「会社や同僚に迷惑をかけてしまう」という強い罪悪感に苛まれる人もいるでしょう。
しかし、その感情に囚われて無理を続ければ、回復が遅れるだけでなく、かえって長期にわたり周囲に心配をかけてしまう可能性もあります。
今、休むことは「逃げ」ではなく、未来の自分と会社のために必要な「戦略的休養」であると捉え方を変えてみることが大切です。
今無理をして心身を壊してしまえば、回復にさらに長い時間が必要となり、結果としてより大きな影響を与えかねません。
「自分の代わりはいても、あなたの人生の代わりはいない」という事実を忘れないでください。
あなたが元気になってまた活躍してくれることこそ、会社にとっての本当の利益になります。
まずは自分自身を大切にすることを許可してあげることが大切です。
休職手続き:具体的な流れと会社への伝え方
適応障害の診断書を手にしたら、次はいよいよ会社へ休職を申し出る段階に入ります。
どのように伝え、手続きを進めれば円満に休職できるのか、不安に思う方も少なくないでしょう。
しかし、ここのステップを丁寧に進めることが、安心して療養に専念するための一番大切な土台づくりになります。
ここからは、以下の3つの流れに沿って、やるべきことを一つひとつ解説していきます。
あなたの心身の負担を少しでも減らしながら、スムーズに手続きを進めるためのポイントを押さえていきましょう。
会社の誰に・いつ・どう伝える?上司への伝え方【例文付き】
休職の意思を会社に伝える際は、まず直属の上司に報告するのが基本的なルールです。
人事部や同僚に先に話すのではなく、組織の系統に沿って報告することで、要らぬ誤解や混乱を防ぎ、誠実な印象を与えることができます。
タイミングとしては、医師から診断書を受け取ったら、できるだけ速やかに上司へアポイントを取りましょう。
他の業務の相談などに見せかけ、「ご相談したいことがあり、15分ほどお時間をいただけないでしょうか」と切り出すと、落ち着いて話せる場を設けやすいです。
報告の際は、感情的にならずに「医師の診断」という客観的な事実を伝えることが大切です。
以下のように、①診断結果という事実、②療養が必要という医師の指示、③引き継ぎへの責任感、という3点を冷静に伝えると、上司も状況を理解しやすくなります。
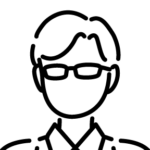
〇〇部長、お時間いただきありがとうございます。実は先日、心身の不調が続いたため病院を受診したところ、医師から適応障害と診断されました。つきましては、しばらく休職して療養に専念するよう指示があり、診断書もいただいております。
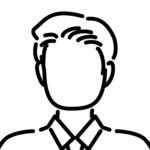 部長
部長そうか。それは辛かったな、話してくれてありがとう。診断書ももらってるとのことだけど、期間はどのくらいの療養が必要だと書かれている?
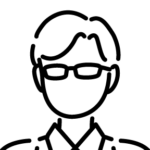
はい、まずは1ヶ月間の休養が必要とのことでした。経過によっては延びる可能性もあるそうです。現在担当している業務につきましては、皆様にご迷惑をおかけしないよう、可能な限り引き継ぎを行いたいと考えております。
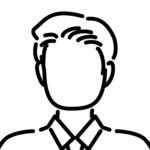 部長
部長わかった。仕事のことは気にせず、まずはゆっくり休んでしっかり治すことを最優先にしてほしい。業務の引継ぎについてはどの程度進められそう?
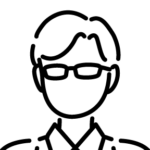
ありがとうございます。正直、あまり余裕がない状況ですが、簡単な引継ぎメモなどでしたら用意できると思います。ただ、十分な資料を作れる自信はありません。
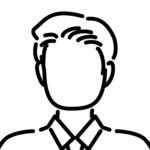 部長
部長それで大丈夫だよ。無理のない範囲で簡単なメモを残してくれればいい。残りの部分はチームでサポートするので、安心してくれ。
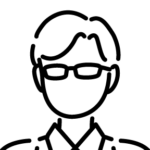
ありがとうございます。本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。
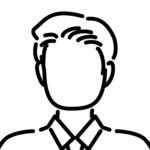 部長
部長気にしなくていいよ。誰でも起こりうることだ。休職中も、何かあればいつでも私に連絡をくれていいから。戻ってくる時は無理のないペースで、焦らず回復に専念してほしい。手続きについては人事部と相談しながら進めていこう。
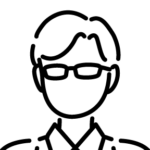
はい、そう言っていただけると本当に助かります。よろしくお願いいたします。
この例文の部長のセリフに「誰でも起こりうることだ」とありますが、実際に日本では仕事が原因で適応障害を引き起こしやすい環境にあると推察する論文も発表されています。
国内調査結果より,労働者が「仕事」「職場での人間関係」に困っていると感じる割合が増加し,気分の落ち込みとの相関が高まっていることが明らかになった。「職場での人間関係」が重視される「メンバーシップ型雇用」である日本の職場は,現代労働者を取り巻く環境の変化により「適応障害」を引き起こしやすくなっていることが推察された。
引用元:日本における「適応障害」患者数の増加|社会政策学会誌『社会政策』第12巻第2号
誰でも起こりうるからこそ、あなた自身を守るための休職であることを、誠意をもって伝えることが大切です。
円満に休むために業務引き継ぎチェックリストを用意する(可能であれば)
あなたが休んでいる間、業務が滞らないように配慮することは、会社との信頼関係を維持し、復職後の人間関係を円滑にする上で欠かせません。
「立つ鳥跡を濁さず」の精神で丁寧な引き継ぎを行うことが、結果的にあなた自身の心の負担を軽くすることにもつながります。
とはいえ、業務の引き継ぎには出社が必要です。
引き継ぎは出来るならやるに越したことはありませんが、医師の「休職が必要という判断」は常日頃から「これ以上の勤務は病状が更に悪化するので働かせられない」という証明でもあります。
どうしても十分な引き継ぎをすることが難しい場合は上司に相談しましょう。
後任者が誰になっても困らないように、常日頃から担当業務に関する情報を客観的な資料として残しておくことが大切です。
以下のチェックリストを参考に、文書で「引き継ぎ資料」を作成しておくと安心です。
| チェック項目 | 引き継ぎ内容の例 |
|---|---|
| 担当業務の一覧 | 業務の名称、進捗状況、今後のスケジュール、直近の締め切り |
| 関係者連絡先リスト | 社内外の担当者の氏名、所属部署、連絡先、関係性の簡単な説明 |
| データ・資料の保管場所 | PC内のフォルダパス、社内共有サーバーの場所、紙書類のファイリング場所 |
| 日常的・定期的な業務 | 毎週・毎月行っている定例業務の内容と手順、報告書のフォーマットなど |
| 各種ツールのID・パスワード | 業務で使うシステムのログイン情報(情報の管理方法は会社のルールに従う) |
| 懸案事項や注意点 | 特に注意が必要な取引先、過去にあったトラブルとその対応策など |
この資料を作成する過程で、自分自身の仕事内容が整理されるというメリットもあります。
やるべきことを「見える化」することで、安心して療養生活に入ることができるでしょう。
休職届の書き方と就業規則で確認すべき3つのポイント
上司への報告と業務引き継ぎの目処が立ったら、会社の規定に従い休職届を正式に提出します。
この段階で、必ず自社の就業規則に目を通し、休職に関するルールを正確に把握しておくことが、後のトラブルを防ぐために重要になります。
休職届のフォーマットは会社によって異なりますが、一般的には所属部署、氏名、休職期間、休職理由などを記載します。
休職理由は「一身上の都合」ではなく、「適応障害の診断を受け、療養に専念するため」などと、診断書の内容と一致させておくとスムーズです。
特に就業規則で確認すべき点は、以下の3つです。
- 休職期間の上限
- 休職中の給与の有無
- 社会保険料の支払い方法
休職期間の上限については、勤続年数などに応じて会社が認める上限が定められています。
まずは自分が最大でどのくらいの期間休めるのかを把握しましょう。
休職中の給与は、多くの企業では休職期間中は無給となりますが、まれに一定期間は給与の一部が支払われるケースもあります。
この規定は、後述する傷病手当金の申請額にも影響するため、必ず確認が必要です。
休職中も社会保険料の支払いは必要だということにも注意が必要です。
給与からの天引きができなくなるため、会社が一時的に立て替え、復職後に精算するのか、あるいは毎月自分で指定口座へ振り込むのか、支払い方法を確認しましょう。
これらの手続きやルールは、あなたの生活に直接関わる重要な事柄です。
不明な点があれば、遠慮せずに人事・労務の担当者に質問し、すべての疑問を解消した上で、安心して休養に入ることが大切です。
最重要!制度活用で休職中のお金の不安を解消する方法
先の見えない療養期間中、収入が途絶えてしまうのではないかと心配になるお気持ちは、とてもよく分かります。
しかし、公的な制度を正しく理解し活用することで、その不安は大きく和らげることができます。
安心して療養に専念するためには、利用できる制度を知っておくことが何よりも大切です。
休職中に利用できる代表的な制度として「傷病手当金」と「休業補償給付」がありますが、それぞれ根拠となる法律や支給の条件が異なります。
| 項目 | 傷病手当金 | 休業(補償)給付 |
|---|---|---|
| 対象となる原因 | 業務外の病気やケガ | 業務上または通勤中の病気やケガ |
| 根拠となる保険 | 健康保険 | 労働者災害補償保険(労災保険) |
| 申請先 | 健康保険組合、協会けんぽ | 労働基準監督署 |
| 支給額の目安 | 給与のおおよそ3分の2 | 給与のおおよそ8割 |
| 社会保険料の負担 | 負担あり | 負担なし |
どちらの制度が利用できるかは、適応障害の原因が業務によるものか、そうでないかによって変わってきます。
まずは、それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
休職中に給料は出ない?基本的なルールを解説
休職を検討する上でまず確認しておきたいのは、休んでいる間の給料の扱いです。
ほとんどの会社では、休職期間中は給与が支払われない「無給」扱いとなるのが一般的です。
これは「ノーワーク・ノーペイの原則」という、労働の提供がなければ賃金の支払い義務も発生しないという考え方に基づいています。
ただし、会社の就業規則によっては、独自の病気休暇制度があり、一定期間は給料の一部が支払われるケースもまれにあります。
ご自身の会社の規定がどうなっているか、必ず人事部や総務部に確認するか、就業規則を直接読んで把握しておくことが重要です。
また、給料の支払いがない場合でも、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)や住民税の支払いは発生します。
支払い方法が給与天引きから個人での振り込みに切り替わることが多いため、その点も併せて確認しましょう。
給料の約2/3がもらえる「傷病手当金」の申請方法と注意点
休職中の生活を支える最も重要な制度が「傷病手当金」です。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガによる療養のため働くことができず、会社から十分な給与を受けられない場合に、ご自身が加入している健康保険から支給される手当のことです。
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である
- 仕事に就くことができない状態である
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
- 休業した期間について給与の支払いがない
申請手続きは、会社の担当部署(人事・総務など)や、加入している健康保険組合のウェブサイトから申請書を入手して進めます。
申請書にはご自身で記入する欄のほかに、医師と会社が証明する欄があるため、それぞれに記入を依頼する必要があります。
申請から振り込みまでには1〜2ヶ月程度かかる場合もあるため、休職に入ったら、できるだけ早く手続きを開始することが大切です。
支給額は給与のおおよそ3分の2で、支給期間は通算で1年6ヶ月です。
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
引用元:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
労災認定は可能?「休業補償給付」との違いと判断基準
もし、適応障害の原因が明らかに仕事上の出来事(例:長時間労働、パワーハラスメントなど)にある場合は、労災保険から給付を受けられる可能性があります。
休業補償給付とは、業務上の原因による病気やケガで働けない場合に、労働者災害補償保険(労災保険)から支給される給付金です。
傷病手当金が「業務外」の原因を対象とするのに対し、休業補償給付は「業務上」の原因を対象とします。
支給額も給付基礎日額(平均賃金)の約8割と手厚いですが、精神障害で労災認定を受けるには、「発病前おおむね6ヶ月の間に業務による強い心理的負荷があった」ことなどを客観的な証拠に基づいて証明する必要があり、そのハードルは決して低くありません。
具体的には、厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて判断されます。
パワハラなどが原因の場合、上司とのメールのやり取りや録音データなど、事実を証明できる記録が重要になります。
ご自身のケースが労災にあたるかどうかの判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署や、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
その他に使える公的制度(自立支援医療など)
傷病手当金のほかにも、療養中の経済的な負担を軽くするための制度があります。
その代表が自立支援医療(精神通院医療)制度です。
これは、適応障害を含む精神疾患の治療のために、継続して通院が必要な方の医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常、医療費の自己負担は3割ですが、この制度を利用すると自己負担が原則1割に軽減されます。
自己負担額
引用元:自立支援医療(精神通院医療)について|自立支援医療(精神通院医療)|東京都福祉局
医療費の原則1割の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
さらに、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられるため、定期的な通院が必要な場合の経済的負担を大きく減らすことが可能です。
申請は、お住まいの市区町村の障害福祉課などの担当窓口で行います。
その他、入院などで医療費が高額になった場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」や、ご自身で加入している民間の生命保険(所得補償保険や医療保険)が使える場合もあります。
利用できる制度を漏れなく活用することが、経済的な不安を解消し、安心して治療に専念するためには不可欠です。
まずは市区町村の窓口や保険会社の契約内容を確認してみましょう。
休職期間の目安と回復フェーズ別の過ごし方
適応障害からの回復には、計画的な休養が欠かせません。
休職は、単に仕事を休むだけでなく、回復の段階に合わせて心と体の状態を整えていくための大切な時間です。
焦る気持ちは当然ですが、回復には一定のステップがあります。
ここでは、休職期間の目安と、3つの回復フェーズごとの過ごし方について解説します。
自分の状態を理解し、一歩ずつ進んでいきましょう。
休職期間はどのくらい?平均的な期間と決め方
「一体いつまで休めばいいのだろう…」と、先の見えない不安を感じるかもしれません。
適応障害での休職期間は人それぞれですが、一般的には3ヶ月から6ヶ月が一つの目安となることが多いです。
しかし、最も大切なのは、期間を自己判断するのではなく、必ず主治医と相談して決めることです。
最初に診断書を提出する際は1ヶ月から3ヶ月程度の期間で設定し、その後は回復の状況を見ながら、医師の判断を仰ぎ延長を検討するのが一般的です。
会社の就業規則で休職可能な期間が定められている場合もあるので、人事部に確認することも忘れないようにしましょう。
焦って復帰を目指すのではなく、専門家である医師と二人三脚で着実な回復を目指すことが大切です。
休養期(~1ヶ月):何もしないことを許可する期間
休職に入ってからの最初の1ヶ月は「休養期」です。
この時期に最も重要なのは、「何もしない」「何もしなくて良い」と自分自身に許可してあげることです。
責任感の強いあなただからこそ、「何かしないと」と焦ってしまうかもしれませんが、今は心と体のエネルギーが完全に尽きてしまった状態です。
まずは、そのエネルギーを充電する必要があります。
| 主な目的 | 心身の安静 |
|---|---|
| 具体的な過ごし方 | とにかく睡眠時間を確保する 栄養バランスの良い食事を摂る 仕事用のスマートフォンやPCから距離を置く 好きなことや心地よいと感じることをする |
この期間は、仕事のプレッシャーや人間関係、将来への不安など、あらゆることから心を解放してあげましょう。
何もしないことに罪悪感を覚える必要は全くありません。
今は「休むこと」が、あなたにとって一番大切な仕事です。
リハビリ期(1~3ヶ月):生活リズムを取り戻す期間
十分な休養がとれて、少しずつ気力が戻ってきたら、次の「リハビリ期」へと移行します。
この段階では、乱れてしまった生活リズムを少しずつ取り戻していくことが目標になります。
ただし、ここでも焦りは禁物です。
社会復帰を急ぐあまり、いきなり高い目標を立てる必要はありません。
まずは「朝決まった時間にカーテンを開けて太陽の光を浴びる」といった、ごく簡単なことから始めてみましょう。
それができたら、次は軽い散歩に出てみる、近所のコンビニまで行ってみる、といったように、少しずつ行動の範囲を広げていきます。
読書や音楽鑑賞、映画など、以前楽しめていた趣味に再び触れてみるのも良いでしょう。
日々の小さな「できた」という体験を積み重ねることが、自信の回復につながっていきます。
調整期(3ヶ月~):今後のキャリアを考える期間
心と体のコンディションがさらに安定してきたら、最後の「調整期」に入ります。
この時期は、復職やその先のキャリアに向けて、社会との接点を少しずつ増やしていくための準備期間です。
日中に図書館やカフェで過ごして体力をつけたり、通勤ラッシュを避けた時間帯に電車に乗る練習をしたりするのも有効です。
そして、この時期に最も大切なのは、「自分は今後、どのように働いていきたいのか」を冷静に見つめ直すことです。
なぜ適応障害になったのか、その原因となったストレスとどう向き合っていくのかを考え、元の職場へ復職するのか、部署異動を希望するのか、あるいは転職して新しい環境を選ぶのか、といった選択肢をじっくり検討します。
必要であれば、職場復帰を支援する「リワーク」施設の利用も視野に入れましょう。
この期間は、未来のあなたを守るための大切な時間です。
休職後の未来を描く3つの選択肢|復職・部署異動・転職退職
休職期間を経て心身が回復してくると、次に見えてくるのは「これからどう働くか」という未来です。
元の職場に戻ることだけが選択肢ではありません。
大切なのは、あなた自身が心穏やかに、そして健やかに働き続けられる道を選ぶことです。
ここでは、あなたの未来につながる3つの選択肢をご紹介します。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況と照らし合わせて考えてみましょう。
元の職場へ復職
- メリット
-
慣れた環境で、給与や待遇が安定している
- デメリット
-
休職の原因が解決しないと再発のリスクがある
部署異動・配置転換
- メリット
-
人間関係や業務内容など環境を変えられる
- デメリット
-
希望の部署に異動できるとは限らない
転職・退職
- メリット
-
ストレスの原因から完全に離れられる
- デメリット
-
経済的な不安定さや新しい環境への適応が必要
どの道を選ぶにしても、焦りは禁物です。
主治医やカウンセラー、信頼できる家族などと相談しながら、あなたの心と体が「これなら大丈夫」と感じる道筋をじっくりと探していくことが大切です。
選択肢1:元の職場へ復職する
多くの人が選ぶのが、元の職場への復職です。
慣れ親しんだ環境で、経済的な安定を保ちながら社会復帰を目指せるという大きな利点があります。
しかし、ただ元に戻るだけでは、適応障害が再発してしまう可能性があります。
そこで重要になるのが、復職をスムーズにし、再発を防ぐための公的な制度や会社の仕組みを活用することです。
スムーズな職場復帰を助けるリワークや試し出勤制度について
復職への不安を和らげるためには、リワークという制度の活用を検討しましょう。
リワークとは、医療機関や地域障害者職業センターなどが提供する、職場復帰に向けたリハビリテーションプログラムのことです。
東京障害者職業センター(リワークセンター東京及び多摩支所)では、平成26年度以降に、3,200人以上がリワーク支援を利用し、毎年80%以上の方が職場復帰を果たしています。
引用元:リワーク支援(メンタルヘルス不調により休職している方の職場復帰)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
オフィスに近い環境で軽作業を行ったり、認知行動療法を用いてストレスへの対処法を学んだりすることで、週5日間、決まった時間に通うというリズムを取り戻し、自信を持って復職に臨む準備を整えることができます。
また、会社によっては、本格的な復帰の前に短時間勤務などから始められる「試し出勤制度」を設けている場合があります。
主治医や産業医と相談の上、これらの制度を上手に利用し、心と体への負担を最小限に抑えながら、ゆっくりと職場に再適応していくことが大切です。
選択肢2:部署異動や配置転換を交渉する
もし、あなたの不調の原因が特定の業務内容や部署内の人間関係にはっきりとある場合、復職と同時に部署異動や配置転換を交渉することも有効な選択肢となります。
慣れた会社組織に籍を置きながら、ストレスの原因となっていた環境から物理的に離れることができるため、再発のリスクを大きく下げることが期待できるでしょう。
再発を防ぐための時短勤務や業務内容調整の相談方法
部署異動や業務内容の調整を希望する場合は、主治医や産業医、人事担当者との復職面談の場が重要な機会になります。
自分の希望を感情的に伝えるのではなく、「なぜ環境を変える必要があるのか」を客観的な事実に基づいて説明しましょう。
例えば、「主治医から、再発防止のためには現在の業務から離れ、負荷の少ない業務への転換が望ましいとの意見を得ています」といった形で、専門家の見解を添えて伝えることがポイントです。
会社側と円滑に話し合いを進めるためには、以下の点を整理して臨むとよいでしょう。
- 伝える内容の例
-
「主治医の診断書に、環境調整の必要性が記載されております。」
- 伝える内容の例
-
「可能であれば、個人での折衝が少ない〇〇部への異動を希望いたします。理由は、対人関係の負荷を減らすことが回復に不可欠だからです。」
- 伝える内容の例
-
「まずは週3日の時短勤務から始め、体調を見ながら徐々に勤務日数を増やしていきたいと考えております。」
自分の状態を正直に伝え、会社側と協力して「働きやすい環境」を再構築していくという姿勢で相談することが、合意形成への近道です。
選択肢3:転職・退職して新しい環境へ進む
休職期間は、これまでの働き方や自分自身のキャリアをじっくりと見つめ直すための貴重な時間でもあります。
「この会社で働き続けることが、本当に自分の幸せにつながるのだろうか」と考えたとき、転職や退職という決断も、あなたの未来を守るための前向きな選択肢になります。
環境そのものを根本的に変えることが、何よりの回復と再発防止につながるケースは少なくありません。
ただし、休職中の焦りや不安から「早く辞めなければ」と結論を急ぐのは禁物です。
まずは心と体の回復を最優先し、十分にエネルギーが充電されてから、冷静に今後のキャリアを考えましょう。
ハローワークや転職エージェントには、休職経験者の転職活動をサポートしてくれる専門の相談員がいる場合もあります。
この決断は「逃げ」や「キャリアの失敗」ではありません。
あなた自身が健やかでいられる場所を主体的に選ぶ、勇気ある一歩なのです。
休職を言い出せない・迷っている方へのケース別対応策4つ
休職を決断するまでには、さまざまな心の葛藤があることでしょう。
「迷惑をかけてしまう」「わかってもらえないかもしれない」といった不安は、一人で抱え込むとますます大きくなっていきます。
大切なのは、ご自身の状況に合った考え方や対処法を知り、一歩を踏み出す勇気を持つことです。
ここでは、よくあるお悩みのケース別に、心の負担を軽くするためのヒントをお伝えします。
ケース1:「人手不足で迷惑をかけられない」と感じる場合
責任感が強く、真面目な方ほど「自分が休んだら職場が回らない」と感じ、ご自身を追い詰めてしまう傾向があります。
そのお気持ちは、あなたがこれまで職場に貢献してきた証とも言えるでしょう。
しかし、何よりも優先すべきは、あなた自身の心と体の健康です。
会社という組織は、本来、誰か一人が欠けても業務が継続できるよう、リスク管理を行う責任があります。
あなたが無理をして心身の調子を崩し、長期にわたって働けなくなることの方が、結果として職場にとって大きな損失となりかねません。
あなたの代わりはいても、あなたの人生を歩む代わりは誰もいないのです。
まずはご自身を大切にすることが、巡り巡って周囲のためにもなる、という視点を持つことが大切です。
ケース2:「上司に理解がなく、言い出しにくい」場合
上司の言動が気になり、休職の相談をすること自体に大きなストレスを感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような状況で無理に話をしようとすると、かえって心が消耗してしまいます。
まずは、あなた自身の安全を確保するルートを探すことを考えましょう。
直属の上司に直接話すのが難しいと感じるなら、必ずしもそのルートにこだわる必要はありません。
人事・労務部や、産業医、あるいは社内のコンプライアンス窓口など、別の相談先を探してみましょう。
診断書は、あなたの状態を客観的に示す強力な証明書です。
感情的に訴えるのではなく、「医師から休職が必要との診断が出ている」という事実を、適切な部署に伝えることが有効な手段となります。
あなたを守るための方法は、一つだけではないのです。
ケース3:「休職すべきか、退職すべきか」で迷っている場合
心身が疲れきっているときは、物事を冷静に判断するエネルギーも枯渇しがちです。
そのような状態で「退職」という大きな決断を下すのは、とても危険なことと言えます。
まず何よりも重要なのは、人生に関わる重大な決断を急がないことです。
結論を出す前に、まずは「休職」という選択肢を取り、心と体を休ませるための時間を確保しましょう。
休職期間は、傷病手当金などの公的制度を利用することで、経済的な不安を和らげながら療養に専念できます。
その上で、心身が回復し、冷静に物事を考えられるようになってから、今後のキャリアについてじっくりと見つめ直すのが賢明な順序です。
もし、休職せずに退職してしまうと、傷病手当金を受け取れなくなる可能性もあり、経済的にも精神的にも追い込まれかねません。
まずは安全な場所で休み、未来を考えるエネルギーを蓄えることが大切です。
ケース4:「家族やパートナーに休職したいことを伝えづらい」場合
最も身近な存在である家族やパートナーだからこそ、「心配をかけたくない」「理解してもらえないのではないか」という不安から、なかなか言い出せないことがありますよね。
しかし、一人で抱え込むことは、かえって孤立を深めてしまうことにもつながります。
伝える際には、「①客観的な事実」「②自分の素直な気持ち」「③具体的にしてほしいこと」の3つに分けて話すことを意識してみてください。
例えば以下のような形です。
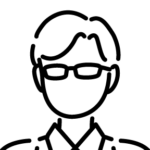
病院で適応障害と診断されたんだ(客観的な事実)
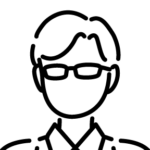
正直、今は仕事に行くのがとてもつらい(自分の素直な気持ち)。
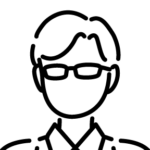
だから、少しの間、休ませてほしい。回復するまで、温かく見守ってくれると嬉しいな(具体的にしてほしいこと)
経済的な不安についても、傷病手当金の見込みなどを共有することで、相手の心配を和らげられます。
勇気を出して打ち明けることが、一番の味方を得るための第一歩となるでしょう。
困った時の相談先リスト(産業医、労働組合、外部相談窓口)
社内の人間関係の中で相談するのが難しい、あるいはどこに話せばよいか分からないと感じたときも、あなたは決して一人ではありません。
あなたの状況を理解し、専門的な立場から力を貸してくれる公的な相談窓口が存在します。
これらの機関は、あなたのプライバシーを守りながら、中立的な立場で話を聞き、解決の糸口を探してくれます。
一人で悩み続けず、ぜひ活用を検討してみてください。
産業医とは、企業に配置され、社員の健康管理や職場環境改善を行う医師のことを指します。
職場でストレスを感じる、メンタル不調がある場合、症状や勤務の負担について相談し、就業上の配慮をしてもらいましょう。
| 相談できること | 職場環境の改善、復職支援など |
|---|---|
| 特徴 | 医学的な専門知識に基づいた助言 |
どの窓口に相談すべきか迷う場合でも、まずはアクセスしやすいところに連絡してみましょう。
そこから、あなたの状況に合った専門機関を紹介してもらうこともできます。
行動を起こすことで、必ず道は開けていくはずです。
適応障害で休職を考えている方のよくある質問
休職中の会社への連絡は、どのくらいの頻度ですれば良いのでしょうか?
休職中の連絡を考えると、心が重くなるお気持ちはとてもよく分かります。
負担にならないよう、休職に入る前に会社と連絡のルールを決めておくことが大切です。
一般的には、月に1回程度の連絡で十分な場合が多いです。
例えば、傷病手当金の申請書を郵送するタイミングで、簡単な近況を添えるといった方法があります。
連絡する相手も、直属の上司か人事部かを確認しておきましょう。
内容も「療養に専念しており、体調は落ち着いています」といった簡単な報告で構いません。
事前にルールを決めておくことで、余計な不安を減らし、安心して休養に専念できます。
回復のために、休職中に「やってはいけないこと」はありますか?
早く元気になりたいと焦るお気持ちから、何か行動したくなるかもしれませんね。
しかし、回復のためには避けるべきこともあります。
特に「休養期」には、以下の4点を意識することが大切です。
- 自己判断で薬をやめること: 必ず主治医の指示に従いましょう。
- 無理に活動すること: 「何かしないと」と焦らず、まずは心と体を休ませることが最優先です。
- 大きな決断をすること: 退職や引っ越しといった重要な決断は、心身が回復し、冷静に判断できるようになってから考えましょう。
- 原因から完全に目を背けること: 回復してきたら、ストレスの原因とどう向き合うかを考える時間も、再発防止には必要です。
やってはいけないことを意識し、焦らずご自身のペースで過ごすことが回復への近道です。
休職すると社会保険料や住民税はどうやって支払うのですか?
休職中は給料からの天引きができなくなるため、社会保険料や住民税の支払い方法が変わります。
これは、お金の計画に関わる重要な手続きです。
- 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料): 支払い方法は会社によって異なります。会社が一度立て替えて復職後に精算するか、毎月あなたが会社の指定口座へ振り込むのが一般的です。休職前に必ず人事・労務の担当部署に確認しましょう。
- 住民税: 前年の所得に対して課税されるため、休職中でも支払い義務があります。多くの場合、お住まいの市区町村から自宅に納付書が送られてくる「普通徴収」に切り替わります。その納付書を使って、ご自身で金融機関やコンビニなどで支払います。
復職面談では、何を話せば良いのでしょうか。うまく話せるか不安です。
復職前の面談は緊張しますよね。
事前に準備をしておくと、不安が和らぎ、落ち着いて話せます。
主に産業医や人事担当者と話すことになりますが、以下の点を整理しておきましょう。
- 主治医の意見: 復職が可能であること、回復状況、働く上で配慮が必要な点などを、ご自身の言葉で説明できるようにしておきます。
- 現在の生活状況: 「毎朝7時に起き、日中は図書館で2時間過ごせるようになった」など、生活リズムや体力が回復していることを具体的に伝えます。
- 復職後の働き方の希望: 時短勤務や業務内容の調整など、再発を防ぐためにどう働きたいか、具体的な希望と理由を伝えます。
- セルフケア: ストレスとの向き合い方など、ご自身で取り組みたい再発防止策を話せると、より前向きな印象を与えます。
産業医や人事はあなたの味方です。
正直に状況を伝え、一緒に働きやすい環境を考える姿勢で臨むことが大切です。
適応障害とうつ病の違いは何ですか?
ご自身の状態を正しく理解することは、回復への第一歩としてとても重要です。
適応障害とうつ病の最も大きな違いは、ストレスの原因がはっきりしているかどうかです。
- 適応障害: 職場の人間関係や過重な業務など、ストレスの原因が明確なのが特徴です。その原因から離れると、症状が比較的すみやかに軽快する傾向にあります。
- うつ病: ストレスがきっかけになることもありますが、原因が特定できない場合も少なくありません。ストレスの原因から離れても、気分の落ち込みや意欲の低下といった症状が長く続く傾向があります。
ただし、適応障害が長引くことでうつ病に移行するケースもあります。
どちらも専門的な治療が必要なため、自己判断はせず、必ず医師の診断に従いましょう。
休職中に転職活動をしても良いのでしょうか。復職か退職か迷っています。
休職中は将来への不安から、復職か退職かで気持ちが揺れ動くことでしょう。
何よりもまず、ご自身の療養に専念することが大切です。
その上で、転職活動についてですが、心身が十分に回復し、主治医から活動の許可が出てから始めるのが原則です。
休職初期の焦りの中で重大な決断をするのは避けましょう。
法的には休職中の転職活動を禁じるものはありませんが、会社の就業規則で兼業などが制限されている場合もあるため、確認は必要です。
面接では、休職の事実を正直に伝えた上で、現在は回復し、働く意欲があることを前向きに説明することが重要になります。
回復という手続きを第一に、ご自身の健康を最優先しながら、キャリアの選択肢をじっくり検討しましょう。
まとめ:適応障害で休職する場合でも一人で抱え込まず自分のペースで進みましょう
この記事では、適応障害で休職を考えるときの、具体的な手続きからお金の不安を和らげる方法、回復に向けた過ごし方、その後のキャリアまでを解説しました。
何よりも大切なことは、休職は逃げ道ではなく、あなたが健やかな未来を歩むために選べる回復のための大切な選択肢だと理解することです。
- 休職を決断してから手続きを終えるまでの具体的なステップ
- 傷病手当金など休職中の生活を支える公的制度の活用法
- 回復の段階に合わせた無理のない休職期間の過ごし方
- 復職・部署異動・転職といった将来のキャリアの選択肢
先の見えない不安で、心が押しつぶされそうになることもあるでしょう。
しかし、あなたは一人ではありません。
まずはご自身の心と体を守るために、勇気を出して専門の医師に相談することから始めてみてください。
![精神・心のケアならココロドック | 島村記念病院 - 練馬区 [ 糖尿病専門外来・小児科・乳幼児健診・予防接種・整形外科・健診・人間ドック ]](https://www.shimamura-hosp.com/kokoro-dock/wp-content/uploads/2025/04/logo-header.png)